「HACCPの考え方を取り入れた衛生管理」の「考え方」って何だろう?②―こう考えればCCP管理をしなくても食品安全を確保できるかも?(私案をいくつか)
更新日時:2025.10.14
では、「HACCPの考え方」とは何か。「HACCPの考え方を取り入れた衛生管理」とは何か?
著者は、実は行政が何を求めているか、(申し訳ないが)寡聞にして知らない。
いや、行政関係者も「HACCPの考え方を取り入れた衛生管理」とは何か?と聞かれて、明確に回答できる人はすくないのでは……と疑ってさえいる。
とはいえ、少なくとも「手引書の通りにやること」ではない。
では、「HACCPの考え方」とは何か? 原則1~7のことか?
たぶん違う。原則1~7をきちんとやったら、それは「HACCPに基づく衛生管理」である。
では、原則2~7の一部だけ取り入れることか?
それは無理だ。HACCPの7原則は、原則1から連なる「一連のもの」である。
「原則1:ハザード分析(HA)」で「これは重要なハザード」とみなされたもの(食中毒菌、アレルゲン、硬質遺物など)について、管理方法を決める(原則2~5)、見直し方を決める(手順6)、記録のルールを決める(手順7)のがHACCPである。
手順1「ハザード分析」をやっていなければ、HACCPではやることは何一つ決められない。
では、「HACCPの考え方を取り入れた衛生管理」≒「ハザード分析の考え方を取り入れる」だろうか? これは、それほど間違っていない気がする。
よく“大企業に向いていそうな”HACCPワークショップ(実質3日間コース)では、ハザード分析シートの埋め方を教える。零細企業や飲食店で、このようなシートを作成する必要はないと思う。
ましてや「記入する順番」を教えるのは、もはや“マナー講座”のようなものである。なぜなら、「どのような考え方でシートを作成するか?」を伝えれば、自ずと「シートに記入する順番」は決まっているからだ。
それはさておき。大事なことは「ハザードを認識すること」ではないか?
腸管出血性大腸菌のリスクを知らないハンバーグ屋、カンピロバクターのリスクを知らない焼き鳥屋、ウェルシュ菌のリスクを知らないカレー屋、アレルギーのリスクを知らない洋菓子店、アニサキスのリスクを知らない鮮魚店……事業を営む資格はない。
前出の食品安全基本法 第八条には「食品関連事業者は(中略)事業活動に係る食品その他の物に関する正確かつ適切な情報の提供に努めなければならない」とある。自社のリスクを知り尽くし、それを消費者に適切に伝えることは、事業者の責務である。
(まあ、第九条では、消費者は食品の安全性の確保に関する知識と理解を深めるとともに、食品の安全性確保に積極的な役割を果たせ、とあるので、消費者も無関係ではないのですが……)
ハザードを認識したら、どのような管理ができるか(CCPを設定しない考え方)
私見ではあるが、事業規模に関係なく、「ハザードは認識しなければならない」。その上で、安全確保の手段を明確化しなければならない。
一方で、CCPを設けると、事業者には大きな負担になる。そこでカギを握るのが「CCPを設けずに、安全確保をする理由付け」ではないか?
例えば、
・「品質管理で十分にハザードのコントロールができるので、CCPにしない」という考え方を利用する。
これは、米国では既に普及している考え方である。
例えばホットケーキを焼く温度は、ハザードをコントロールするためではなく、品質のために設定されている。しっかり焼かないとフワフワにならない。ホットケーキを焼く温度・時間であれば、一般的な食中毒菌は余裕で死ぬ。温度が低ければ、ベチャベチャのホットケーキで、そもそも販売されるはずがない。ゆえに、この焼成工程をCCPで管理する必要はない(はずである)。
同様の考え方は「米を炊く」「うどんを茹でる」「食品を凍らせる」「高温で揚げる」といった工程にも使えるだろう。(注:もちろん、これらの工程をCCPにしても問題はない)
・上記の考え方を一歩進めて、「官能評価で出荷・提供の判断をくだす」
特に弁当屋や飲食店では、この考え方が利用できるのではないか。飲食店では、調理後、すぐにお客様に食事を提供する。
例えば、ピンクの肉汁のハンバーグを出すことは(家庭の料理でも)あり得ないだろう。半なまの鳥の唐揚げを出すことはあり得ないだろう。加熱用の食材を、生焼け、生煮えの状態で出すことはあり得ないだろう。
官能評価は、本来は「極めて高精度なモニタリング手段」である。官能評価で問題ない料理を、その場ですぐに食べてもらうのであれば、ほとんどの場合、食品安全上のリスクは起こらないと許容できるのではないか?
・金属探知機については、一般衛生管理との組み合わせで考える
「金属探知機=CCPにしたい」という思い込みが、日本では根強い。中には、HACCPを正しく理解した上で「金探をCCPにしなくてもいいけど、金探は設置してほしい」「そうして金探を設置したなら、金探をCCPにしておけばいい」という理屈もあるようだ。
金探を設置しないのであれば、やはり「ハザード分析」がカギを握る。
ハザード分析で「どこから金属の混入の可能性があるか?」を把握して、その場所で一般衛生管理を徹底すればよい。包丁の刃がかける可能性があるなら、日々の作業の中に「包丁の欠けがないか目視で点検する」を入れればよい。特に飲食店であれば、過去のクレーム、他店のクレームを参考に、ハザードの混入箇所を把握できているのではないだろうか。
それはさておき。では、飲食店で、お客様に料理を出す前に金探を通している店はあるだろうか?(あるのかもしれないが)
なぜ、加工食品では「金探=CCP」がまかり通るのに、飲食店ではそれを要求しないのか?
実は、著者は、何人かの専門家にこの質問をしたことがある。ほとんどが鼻で笑われた。笑われた上で、誰も答えは教えてくれなかった。
たぶん理由はないのはないか? 「置く場所がないから」か言われたことはあるが、小型の金探はある。「高価だから」とボソリといわれたことはあるが、「CCPの逸脱はヒトの命に関わる」のではなかったか?
・記録は出来るだけ効率化する(最小限でよい?)
HACCPで根強い誤解は「HACCP=何でもかんでも記録」という考え方である。
最小限の記録は何か? 例えば、取引先が求める記録が何かを聞いてみればよいのではないか?
なぜHACCPで記録が必要か?
理由は主に2つではないか?
①衛生管理を後から見直すため(クレーム対応時の証拠としても必要)
②「記録がなければ『その作業をやっていない』とみなされても文句は言えないから
①と②は連動している話だが、いずれにしても「後から見直さない記録は必要ない」と割り切っても良いのではないか?
例えば、飲食店であれば、厨房に入る人、接客する人の健康管理や手洗いの記録は、ノロウイルスの話題になった時に必要だろう。
調理で「ちゃんと官能評価をした」という記録は、大腸菌やサルモネラの話題になった時に必要だろう。
何でもかんでも記録できれば、それはそれで助かるだろう。だが、最初からすべての記録を残すのはしんどいはずだ。「出来るところから始める=絶対に必要な記録はどれか?」を吟味できれば、記録付けはスタートしやすくなるのではないか?
・HACCPのアプローチは「流通する食品」と「すぐに食べる食品」で違うはず
そもそもHACCPのやり方を「50人」という人数で区切ることがナンセンスなのである。
例えば、シュークリームを販売する。それを全国に発送したら、それは家族経営の店舗であっても「HACCPに基づく衛生管理」でなければならないだろう。
2023年に「イベントで糸引きマフィン」が話題に上がったことがある。
もし「店舗で作って、その場で食べてもらう」「テイクアウトは出来るが、保冷剤を入れて、帰宅したら冷蔵庫に入れて、その日のうちに食べてもらう」というのであれば、上に述べたような考え方を取り入れて、CCPのない製造工程にしても(多くの場合は)問題はないだろう。
しかし、「大量に作る」「消費者がいつ食べるか分からない」という状況があるなら、製法は「HACCPに基づく衛生管理」にして、「食べ方」に関する約束事をラベルに明示すべきであろう。
・何かを変えたらハザード分析を考え直す。「すぐに食べる食品」でも、量が増えたら話は変わってくる
例えば、「家庭の味のカレー屋さん」が人気を博して、事業規模を少し大きくしたとする。
もし、鍋を深くしたなら、あるいは新メニューとして前よりもトロミを付けたりしたら、「今までの製法でウェルシュ菌対策は大丈夫か?」を見直さないといけない。「鍋を深くしたらウェルシュ菌の毒素が発生した」という話を聞いたことがある。
零細規模で「ハザード分析シートを作れ」「ハザード分析シートを作り直せ」という必要はないと思う。しかし、ハザードの『認識』はしていなければならない。
こうした考え方が、Codexの「食品衛生の一般原則」から、著者が考えた「HACCPの考えたを取り入れた衛生管理」に取り入れられそうな「HACCPの考え方」である。
いかがでしょうか?


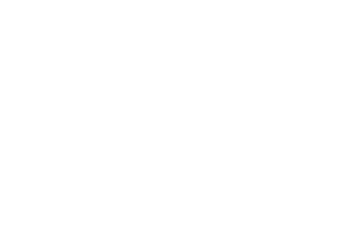 お問い合わせはこちら
お問い合わせはこちら