病原菌環境モニタリングプログラムという考え方②―補足編:定量的にデータを追いかけ、傾向を捉える
更新日時:2025.10.13
環境の微生物検査やATPふき取り検査など、定量的な汚染指標の把握を継続的に実施すると、何らかの傾向(トレンド)が浮かび上がることがある。こうなると、現場の衛生改善に向けた「大きなチャンス」を手に入れたことになる。
例えば、何日にもわたりふき取り検査を実施したところ、あるとき突然、菌数が増えたとする。そうなると、そのタイミングで「何か特殊の状況があったのでは?」と考えられる。
一方で、数日をかけて徐々に菌数が高くなっているのであれば、「徐々に菌が蓄積している」という状況が推察できるので、基準値を逸脱する前に対策を打つことができるかもしれない。
例えば、加工装置の分解洗浄が不足していたら、徐々に菌数が上がってくるかもしれない。菌数が高い日に、何らかの共通点が見つかるかもしれない(例えば、特定の作業者が勤務している、特定のメーカーの原材料を使っている、休日明けの曜日だけ菌数が高い、など)。
ムービング・ウインドウ(moving windows)という考え方
こうした傾向を把握する際に、最近、品質管理の分野では、ムービング・ウインドウ(moving windows)という考え方が広まっている。これは一般生菌数や衛生指標菌を対象として、3階級のサンプリングプランを適用する考え方である。
サンプリングプランには2階級法と3階級法がある。
2階級法は、1ロットから決められたサンプル数(n)の検査を行い、「基準値(m)を超えるものが一定のサンプル数(c)に納まっていれば合格」とする考え方である。
3階級法は、基準値(m)に加え、第二基準値(M)を設定し、「n個の検査で基準値(m)の逸脱はc個までは許容する(ただしMを超えた場合は不合格とする)」という考え方である。
ムービング・ウインドウの考え方の一例を紹介する。文字だけでは分かりにくいかもしれないが、ご容赦いただききたい。
==============
・毎日、1サンプルずつ検査すると仮定する(注:mやMを超えた場合の対応策は、あらかじめ決めておく)。
・直近の5サンプル(5日間)の検査で、c=2と設定する。その場合、1回mを超えたとしても、即座に生産停止などの厳しい判断をする必要はない。「今回は洗浄の強化などの対応をとればよい」といった対処をとる。ただし、Mを超えた場合は、それが1回目であっても生産停止やHACCP計画の見直しなど、厳格な対応をとる。
・直近5日間の検査で2回、mを超えた場合は、生産停止やHACCP計画の見直しなど、厳格な対応をとる。
==============
以上のように、「1~5日目」「2~6日目」「3~7日目」といたように「5日のフレーム」を設けて、1日ずつ順にフレームをずらしながら評価する。この方法であれば、日々のサンプル数は少なく、かつ継続的な調査、トレンドの把握が可能になるかもしれない。
これは、今後、衛生指標菌を用いた環境検査で注目される考え方になってくるかもしれない。その際、毎日、少量の定量検査を行うため、培地の調製が不要で、手順が簡単な方法であることが望ましい。ATPふき取り検査や簡便・迅速培地など、継続的な定量検査が可能なキットやツールがあれば、この考え方は有効かもしれない。


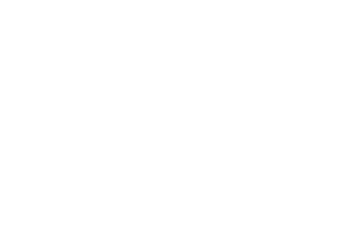 お問い合わせはこちら
お問い合わせはこちら