ハザード分析、何が難しい?
更新日時:2025.10.15
よく「中小零細規模の企業では、ハザード分析が難しい」と言われます。それは一概に否定できることではありません。たしかに、ハザードを漏れなくリストアップしたり、それらの適切な制御手段や管理手段を確立するのは、科学的根拠が必要であり、難しい作業です。
それでも、自社の商品について「重大なリスク」を把握せずに経営していることはないはずです。ハザード分析でやることは、ザックリいうと
①発生する可能性があるすべての潜在的なハザードを挙げる
②ハザード分析を行い、重大な(significant)食品安全ハザードがあれば特定する
③同定されたハザードをコントロールするための手段を考える
という3段階です。言葉にすると難解に感じるかもしれませんが、要するに「リスクの因子を漏らさず把握して、対策を打つ」ということです。
自社の製品で事故を起こさないためには、ハザード分析は必ず実施する作業です。これは、食品業界だけではありません。全てのビジネスでやっていることです。
ですが、いきなり「リスク因子を掌握しましょう」とか言われても、困惑してしまうかもしれません。そこで、参考資料として使われているのが、業界団体が作成している手引書です。
HACCPはフレキシビリティのある(柔軟な、弾力的な)運用が求められます。例えば、
・HACCPチームに、外部の専門家に参画してもらう
・似たような特性の製品は、グループとしてまとめて、フローダイアグラムを作成する
・似たような特性の製品は、グループとしてまとめて、ハザード分析を行う
といったことも、フレキシビリティの一環です。
そして、HACCPでは「行政や業界団体が、(事業者の)代わりにハザード分析を行い、モデル的な仕組みを示せばよい。そのモデルに従っていれば、HACCPをやっているとみなす」という考え方が許容されています。これもフレキシビリティの一環と言えるでしょう。
日本の食品衛生法のHACCP制度化では、手引書が、この「モデル的な仕組み」に相当します。ゆえに「手引書通りにやっていれば、HACCPをやっているとみなされる」という理屈になるのです(と筆者は理解しています)。
ただし、「ハザード分析をやらないHACCPは存在しない」と認識すべきでしょう。
そうである以上、最初のうちは手引書に従うにしても、将来的には「なぜこの手引書の内容で『HACCPをやっている』とみなされるのか?」「この手引書は、どのようなハザード分析の結果なのか?」ということを理解しなければならないはずです。
手引書を入り口にして、そこから“卒業”することこそが、本当の意味でも「HACCPの取り組みのスタート」になると思います。
上記とは別次元の話ですが、もしかして「ハザード分析が難しい」のではなく、「ハザード分析の書式の作成が大変」という状況で困っていることはありませんか?
だとしたら、それはHACCPの本質から離れた悩みです。「キレイな書類を作成すること」を目的にする必要はありません。書類作成に忙殺されながらHACCPを運用していても、きっと真価を発揮できません。
大事なのは、その企業の食品が安全性を確保することであり、その結果として会社が儲かることです。


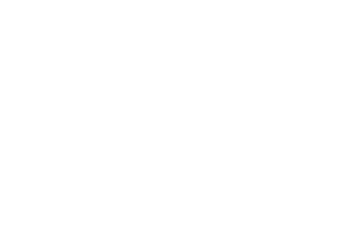 お問い合わせはこちら
お問い合わせはこちら