手順1~5はやらなくてよい?
更新日時:2025.10.18
「食品衛生法で求めるHACCP」と「コーデックスHACCP」は全く同じ、というわけではありません(と著者は認識しています)。ですから、HACCPのセミナーや勉強会に参加する際には、「何を根拠にしたカリキュラムか?」ということは確認する必要があります。
例えば、コーデックス規格の最新版(2020年版、2022年版)には「食品安全文化(フードセーフティ・カルチャー)」や「より注意が必要な一般衛生規範(GHP with greater attention)」といった概念が盛り込まれています。
しかし、日本の食品衛生法に、そういった文言はありません。
同様に、日本の食品衛生法で規定されるHACCP制度化では、HACCPの7原則12手順のうち「手順1~5」は求められていません。手順1~5は「HACCPの準備段階」といわれるプロセスです。
手順1 HACCPチームの編成
手順2 製品の記述
手順3 意図する用途の同定
手順4 フローダイアグラムの作図
手順5 フローダイアグラム現場確認
という手順です。
これらは法律では求められていません。では、手順1~5には取り組まなくてもよいのでしょうか?
手順1~5に取り組まなくても「法律違反ではない」とは言えるでしょう。しかし、ハザード分析から始まる7原則に取り組む上で、手順1~5は自ずと取り組むことになるのです。
ハザード分析を実施する上で、「誰が食べるか」「どのように流通させるか」「どのように製造しているか」といった情報は不可欠です。調理して目の前で食べてもらうのか、消費期限が数日あるのか。不特定多数が食べるのか、病院で抵抗力の弱いヒトが食べるのか。ハザード分析の結果は、全く異なってきます。
HACCPチームに相当する組織がなければ、食品安全の責任者は心身ともに疲弊・崩壊するかもしれません(チームは1人でもよいですし、社外から参画してもらっても構いません)。
いくら現場でHACCPチームが奮闘しても、そもそも経営層が食品安全に対してコミットしていなければ、遅かれ早かれ、その会社のHACCPは立ち行かなくなるでしょう。
一方で、これらの手順は「新規に書類を作れ」という話ではありません。組織図や施設図面、規格書や工程フローなどは、すでに作成してあるでしょう。それらを利用すれば問題ありません。大事なことは、HACCPをやるために必要な情報を収集・確保することです。
「HACCPをやる」ということは、「何か新しいことを始める」というよりは、「自社の製品が、なぜこれまで事故を起こしてこなかったか?」の裏付けをとる、根拠づけをする、というスタンスで取り組めばよいのではないでしょうか?


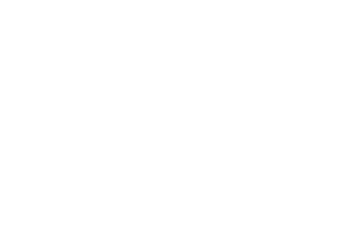 お問い合わせはこちら
お問い合わせはこちら