食品安全文化に関する雑感~性善説・性悪説では議論しない
更新日時:2025.10.17
余談ですが、食品安全文化を「性善説」「性悪説」の観点から論じるのは、あまり意味がないと思っています。
ザックリ印象だけで言うと、孟子の「性善説」を「ヒトの本性は善であり、ヒトを信じるべきという考え方」、荀子の「性悪説」は「ヒトの本性は悪であり、他人は疑ってかかるべきという考え方」と解釈している人が多いようです。
そのため、よく「欧米は性悪説の国。HACCPは性悪説で構築するもの」「日本は性善説が根差している。HACCPのような考え方はなじまない」といった表現を耳にします。
例えば、食品防御(フードディフェンス)の対策として監視カメラを設置すると、従業員から「私たちを疑うのか?」と不満が上がる、といったお話を聞くことがあります(「フードディフェンスの選択肢は監視カメラだけではない」ということは、別の回でお話します)。
ただ、対策を講じることと、性善説・性悪説は関係ありません。性善説では「ヒトを善と信じるべき」とは言っていません。性悪説では「ヒトを悪と疑え」とは言っていません。そもそも「性悪説」の「悪」は、「悪事」や「悪行」ではなく、いわば「弱い存在」といったニュアンスだと思います。
性善説/性悪説は、「生まれながらの本性は変えられなくても、後天的努力、教育によって、身を正すことができる」という解釈でよいのではないでしょうか?。
つまり、生まれながらの善/悪はどうあれ「教育が大事」という結論でいかがでしょう?
ある企業では、食品テロ対策を構築する際、「性弱説」という表現を用いました。「ヒトは生まれながらにして心の葛藤や誘惑によって行動する欲望的存在」といったような意味合いでしょうか。
心の弱さのせいで悪行を犯さないためには、「悪行を許容しない、相互に指摘し合える」「ネガティブな報告を改善に生かせる」という組織的な、人間関係的な環境整備も必要でしょう。
ついでに、もう一つ余談ですが、最近のセミナー等では、チェルノブイリの原発事故の後に構築された、工学分野での「安全文化」の考え方を参考にした説明もあります。この辺り、個人的にはしっくりきません。
「食品安全文化」が求めているのは「食品製造の安全文化」というよりは、「食品安全を組織の文化にする」というニュアンスだと思うからです。「食品/安全文化」というよりは、「食品安全/文化」であり、「食品安全を第一に考える組織風土を醸成する」というくらいの捉え方でよいのではないでしょうか?
そもそも、食品安全文化は海外から流入してきた考えです。「文化」という言葉は、海外と日本では異なるという声も聞きます。海外で文化というと、耕して興すもの、人が築き上げるものですが、日本では自然発生的に醸成されるもの、という色合いがあるようにも思います。
食品安全文化について論じる時、まずは「文化」という言葉の意味を共有することから始めなければならないのかもしれません。


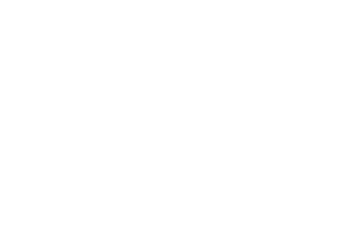 お問い合わせはこちら
お問い合わせはこちら