病原菌環境モニタリングプログラムという考え方①
更新日時:2025.10.13
環境検査の「菌の検出」=「検査の成功」という考え方~検査結果をHACCPの改善に生かす~
海外では、リステリア・モノサイトゲネス(以下LM)やサルモネラ属菌のような、「工場内の環境に常在する微生物」による病原菌汚染のリスク(食品安全上のリスク)が想定される場合には、それの汚染状況を調査する活動が、一般衛生管理の一部として必要な場合があります。
これらの調査活動は「病原菌環境モニタリングプログラム」(Pathogen Environmental Monitoring Program、PEM)と呼ばれており、FSSC 22000などの国際的な食品安全規格でも取り入れられています(工場環境プログラム、環境モニタリング、環境調査プログラムなど、様々な表現がありますが、同じ意味です)。
目的は「バイオフィルムを作る前に、菌を除去すること」
PEMの目標は、病原菌が巣を作る(バイオフィルムを作る)可能性がある箇所を特定し、排除することです(こうした箇所を「ニッチ」などと表現することもあります)。ニッチが見つかったら、そこを重点的にクリーニング、サニテーションすることになります。
活動の目的は「病原菌が巣を作らない、環境に常在しないようにすること」です。そのため、「汚染リスクを検知すること」がきわめて重要となります。
例えばLMの汚染リスクが考慮される工場であれば、検査対象をLMに限定せず、リステリア属菌とする場合もあります。サンプリングはランダムに行うのではなく、「巣になりそうな場所」を中心に行うことが肝要です。
環境調査のサンプリング箇所(ゾーン分けの考え方)
サンプリング箇所については幾つかの考え方がありますが、例えば「4つのゾーン」に分けるアプローチがあります。絶対に避けなければならない状況は「製造ラインや調理器具などの『食品接触面』(Food Contact Surface、FSC)からLMが検出されること」です。しかし、LMがいきなり食品接触面で湧くはずはありません。LMは「原材料やヒト、器材などを介して、食品接触面に持ち込まれる」のです。ゆえに、「LMが食品接触面に近づかないように管理すればよい」のです。
そこで、まずは「食品接触面」を「ゾーン1」に設定し、そこを中心にリスクに応じてゾーン2~4へと広げていきます。
ゾーン1は「食品接触面」です。製品に実際に触れる機器や器具だけでなく、食品に触れる手袋なども該当します。ちなみにAIB(米国製パン研究所)という組織では、食品接触面が存在する箇所は上空も含めて「プロダクトゾーン」と定義して、重点的に衛生管理することを推奨しています。
ゾーン2は、製品接触面に近い周辺です。ラインの周辺から管理パネル、小型器具、装置のハンドルなど、ゾーン1に影響を及ぼす可能性がある箇所を「ゾーン2」として警戒します。例えば、食品を入れる容器は、内側は食品に接触するのでゾーン1となりますが、外面は接触しないのでゾーン2になるかもしれません。リステリア属菌は、基本的に製造環境のどこにでもいます。特に水回りには警戒が必要です。水が飛び散る箇所や、排水溝なども、モニタリングの際には目を光らせると良いでしょう。
ゾーン3は、ラインから離れた箇所、例えば加工室内の電話、フォークリフト、床、壁、排水管、廃棄物容器、ゴミを運搬するカートなどが該当するかもしれません(ゾーン分けに明確な定義はないので、ゾーン2とゾーン3はケースバイケースで設定すればよいです)。ゾーン間を移動する従事者や乗り物、カートなどは、汚染を持ち込む可能性があるので、ヒトやモノの動線にも配慮が必要である。
ゾーン4は、そのさらに外側、加工室の外などです。
こうした「4つのゾーン」という考え方のほかにも、「菌が常在する可能性がある箇所」(growth niches)か、あるいは「菌が常在はしない、一過性の箇所」(transfer site)の2つのゾーンで区分するような考え方もあります。
「菌の検出」=「改善箇所の早期発見」=「検査の成功」
ここで大事なのは「検出は調査の成功である」「検出されたら、そこを中心に洗浄・消毒する」「プログラムの運用では、絶えず検出しようと努力する」という考え方です。
環境調査、環境モニタリングでは、クリティカルなゾーン(ゾーン1など)に病原菌が汚染しないよう、ゾーン2~4で指標菌などをうまく活用することが求められます。そのため、「ゾーン1以外の箇所で指標菌が検出されたら、リスクの兆候を早期に認識できた。未然に対策を講じればよい」と考えることが可能なように、検査のプログラムを構築しておけばよいのです。
すなわち、「指標の検出」=「食品安全上リスクが顕在化する前に、改善すべき箇所が見つかった」ということであり、それは「検査の成功」とみなすことができるのです。
逆にいえば、全ての検査箇所で「不検出」「陰性」であった場合、改善する箇所が見つからないので、「では、別の箇所を検査しよう」と戦略を変更することが求められるのです。陽性があったからといって、すぐに「病原菌コントロールシステムの欠陥がある」と結論付ける必要性はありません。大事なことは、検査の目的を明確に持ち、「検査結果をHACCPや一般衛生管理の改善に活用する」という考え方です。
もちろん、陽性が見つかった時に慌てないよう、「検出された時の対応手順」など、あらかじめ戦略を構築しておくことが求められます。
そして、先ほど述べたようにリステリア属菌は、環境のどこにでも存在する可能性がある菌です。調査は、長期的・継続的に実施する姿勢が必要です。
リステリア・モノサイトゲネスは、日本では食中毒の原因菌としてあまり警戒されていません。しかし、海外では頻繁に死者を伴う集団食中毒が報告されている菌です。2017~18年には、南アフリカで1,000人以上が感染し、180人が死亡するような事例もありました。いつまでも「対岸の火事」と思っていることはできないと思います。
とはいえ、過度に恐れていては、何も始められません。まずはハザード分析の時に、食品安全ハザードとしてインプットすることから始めればよいでしょう。


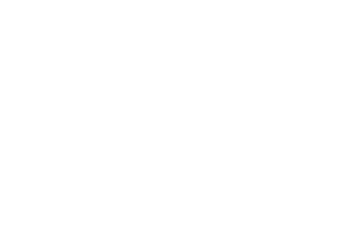 お問い合わせはこちら
お問い合わせはこちら