「見えないリスク」を見える化する②―ATP検査が必ずOPRPになるとは限らない
更新日時:2025.10.13
「『見えないリスク』を見える化する①」からの続きです。
環境由来の食中毒リスクの代表格は「洗浄不十分による病原微生物の交差汚染」と「洗浄不十分によるアレルゲンの交差接触」です。
要は、製造する製品を切り替える際に洗浄を行いますが、その洗浄が不十分なせいで、アレルゲンや微生物が残留し、それが次の製品に移行することです。
ふき取り検査の対象の考え方
それはさておき。交差汚染/交差接触を予防するための手段は、何も微生物やアレルゲンの検査だけではありません。別の指標を用いることでも、十分に代替可能です。
微生物検査では、従来の培養法では、結果が出るのに時間も手間もかかり、リアルタイムでの清浄度確認ができません。そこで、代替の指標を考えます。例えば、「食品残渣がなくなれば、微生物が増殖する餌がなくなる」と考えて、タンパク質の残留をチェックしたり、食品残渣に含まれるATP(アデノシン3リン酸)と呼ばれる化学物質を測ることは、今の技術では簡単に実施できます。
一方、アレルゲン検査では、ELISA法による検査は、時間も装置も必要なので、現場のリアルタイムでの清浄度確認ができません。イムノクロマト法のキットであれば、簡単かつ高感度に、特定のアレルゲンの有無が判定できます。ただ、特に零細事業者ではイムノクロマト法のキットを洗浄の都度使うのは、コスト的に負担になる可能性もあるでしょう。そこで、(アレルゲンもタンパク質ですから)タンパクふき取り検査やATPふき取り検査で代替可能な場合もあります。
ただし、ここで最も大切なことは、洗浄後の洗い残しをなくす第一歩は、「決められた洗浄手順の遵守」と「洗浄後の目視確認」であるという点です。これらをキチンとやって、初めてふき取り検査が意味を為します。
洗浄後に、目視やにおいなど官能的な問題があれば、そもそも検査をする意味がありません。検査キットは「『見えない汚れ』を『見える化』するツール」なのですから、「見えてる汚れ」を検査しても、何の意味もありません(衛生教育としての意味はあるかもしれませんが)。
OPRPはハザード分析の結果として決まる
洗浄後のATPふき取り検査をOPRPに設定している現場もあります。ハザード分析の結果として、「この装置では、洗浄不備があると潜在的な食品安全ハザードが懸念される」と判断したのであれば、そういう選択肢もあるでしょう。しかし、「洗浄後のATP検査=OPRP」「洗浄後のATP検査=特に注意を要するGHP(適正衛生規範)」と安直に考えては本末転倒です。
ATP検査で、その装置の全ての表面の清浄度が確認できるわけでもありません。洗浄するごとにATP検査をルールにしたら、コスト負担になるかもしれません。
洗浄後は、まずは目視確認で異常がないかを確認し、それから時々は(目視以外の方法で)検証するようにするとよいでしょう。
ISO 22000/FSSC 22000では、ハザード分析の結果として、①一般衛生管理(PRP)として管理するか、②OPRPとして管理するか、③CCPとして管理するか、が決まります。
コーデックスHACCPであれば、ハザード分析の結果として、①PRPとして管理するか、②特に注意を要する適正衛生規範(GHP with greater attention)として管理するか、③CCPとして管理するか、が決まります。
食品衛生法への対応であれば、ハザード分析の結果として、①PRPとして管理するか、②CCPとして管理するか、が決まります。ただし、HACCPは自主管理ですから、OPRPやGHP with greater attentionの考え方を適用するのは自由です。自社の製品や製法、衛生水準などを考慮した管理体制を構築しましょう。
ふき取り検査の留意点
そして、ふき取る箇所は「汚れが残りやすい、溜まりやすい箇所」「洗い残しが生じやすい箇所」であるべきです。きれいな包丁の、平滑な面をふき取っても、おそらく「きれいな結果」しか出ないでしょう。それでは意味がないのです。
窪んだ箇所、凹凸がある箇所、ヒトが頻繁に触れる箇所(「高頻度接触表面」とじゃ「ハイタッチポイント」とか言うこともあります)など、「悪い結果が出る可能性がある箇所」こそが「汚染リスクがある潜在的な箇所」になるのです。そういう箇所こそ、ふき取るべきです。
そして、ふき取り検査は「我流」であってはなりません。ふき取り方、ふき取る圧力など、あらかじめルールを設けておくべきです。
【用語解説】
①「交差汚染」と「交差接触」
交差汚染はcross contaminationの訳語、交差接触はcross contactの訳語です。起きている現象はcross contaminationもcross contactも同じですが、食物アレルゲンが意図せず移行することをcross contactと表現します。
そもそもアレルゲンは「食べられる成分」であり、単なる汚染物ではありません。アレルゲンの意図せぬ移行は(アレルギーを持たない人にとっては)汚染ではないので、「微生物の意図せぬ移行=交差汚染」「アレルゲンの意図せぬ移行=交差接触」と、言葉を別々にしているようです。
②ATPふき取り検査
ATPとは、全ての有機物に含まれる化学物質です。そのため、食品残渣、微生物、ヒトの皮膚や体液など、あらゆる有機物をまとめて測る方法です。実際にATP検査を実施している現場では、菌のリスクを測るというよりは、菌が増殖する栄養源となる食品残渣をなくすための指標として使われています。この背景には、菌よりも食品残渣の方が、含有するATP量が多い、という事情もあります。
アレルゲンの管理でATPふき取り検査を用いる場合、食品の種類によってATPの含有量は差があることや、ATP検査の反応を阻害する物質も存在するため、導入前には確認が必須です。


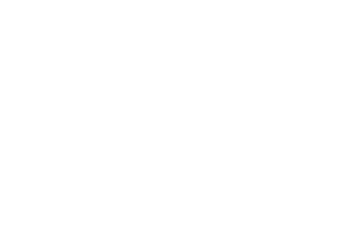 お問い合わせはこちら
お問い合わせはこちら