「見えないリスク」を見える化する①~検査結果で「現場の衛生意識」を改革できる~
更新日時:2025.2.11
食品現場で注意すべき一般衛生管理の項目(主に9つ)
食品現場に目を向けると、多くの食品事故(食中毒、異物混入など)は、工程管理(HACCP)の不備というよりも、むしろ一般衛生管理の不備に原因であるといわれています。図は、厚生労働省が飲食店で発生した食中毒の原因を9項目に分類したパンフレットです。
また、その9項目を、いわゆる「食中毒予防の3原則」(つけない、増やさない、やっつける)と対照させています(ちなみに、ノロウイルス食中毒の予防の場合、3原則に「持ち込まない」を付けて「4原則」としている場合があります)。

この9項目のうち、どれをHACCP計画で扱い、どれを一般衛生管理で扱うかは、ハザード分析の結果で決まりますが、飲食店では加熱不十分によるカンピロバクターや病原大腸菌による食中毒、手洗い不十分によるノロウイルス食中毒、保管時(再加熱前)の温度不備によるウェルシュ菌食中毒などが、特に問題となります。
そのため、赤色の「やっつける」のうちの「適切な加熱」、青色の「増やさない」のうちの「低温で保存」を除けば、おおむね「一般衛生管理」で取り扱うことになるでしょう(最近はアニサキス食中毒も多いですが、アニサキスは適切な冷凍または加熱で予防できるので、また別の回でお話します)。
これが「飲食店では一般衛生管理が重要」と言われる理由の一つです。
「見えないリスク」で要警戒は病原微生物とアレルゲン
さて、こうした一般衛生管理のうち、特に環境の洗浄不足による食中毒菌や食物アレルゲンの残存、不十分な手洗いによる微生物の残存は、重大な食品事故につながる可能性があります。
食品現場では、そうした重大なハザードを確実に実施しなければなりません。しかしながら、微生物や食物アレルゲンは「小さすぎて目視できないリスク(ハザード)」です。現場スタッフの衛生管理に対する意識を高めるには、こうしたリスクを認識できるよう「見えないリスク」を“見える化”(可視化)することが非常に有効な手段となります。
しかし、培地を用いた微生物検査や、ELISA法によるアレルゲンの定量検査は、時間も手間もかかります。衛生教育をしようにも、作業後、数日経ってから「あの日の洗浄は~」と指摘されても、数日前の行動の記憶は曖昧でしょうし、なかなか臨場感のある教育にはなりません。
そこで、効果を発揮するのが、ATPふき取り検査やタンパクふき取り検査、イムノクロマトキットによるアレルゲン検査、蛍光塗料を用いた手洗い教育、プレパラート不要でポケットサイズの顕微鏡(スマートフォンで観察する「携帯形微生物観察器」)といった、「その場で、結果が数値化または視覚化できるツール」です。
洗浄後の衛生点検の基本は、まずは「視覚」「嗅覚」「触覚」など五感を駆使した官能評価です(目視確認、異臭がないか確認する、異物がないか触ってみる、など)。
その上で、科学的な評価方法を効果的に組み合わせることで、ワンランク上の「洗浄後の清浄度確認」の仕組みを構築できます。
そして、そうした検査結果を衛生教育の際に活用することは、「衛生管理水準の向上」と「現場スタッフの衛生意識の改革」という、何物にも代えがたい大きなメリットをもたらします。


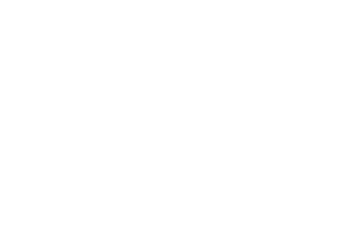 お問い合わせはこちら
お問い合わせはこちら