「HACCPの考え方を取り入れた衛生管理」の「考え方」って何だろう?③――「HACCPの考え方~」はHACCP?HACCPじゃない?
更新日時:2025.10.14
最後に、少しひねくれた考えを披露する。ひねくれているので、関係者は、気を悪くされずに、一笑に付していただきたい。
「HACCPの考え方を取り入れた衛生管理」。この言葉は「取り入れればよい」と読むことができないだろうか? つまり「考え方を取り入れただけで、HACCPではない」という解釈はできないだろうか?
……という考え方である。
2018年にHACCPが制度化されたが、行政は、制度の設計者は「零細規模、飲食店でHACCPの7原則を義務付けるのは難しい」とわかっていたはずだ。
つまり、「7原則の適用が出来ないのはわかっているけど、せめて『考え方』くらいは取り入れてほしい」という意図はなかっただろうか?
そうであれば、事業者が最初に読むべきは、食品安全基本法や食品衛生法などの国内の法律を別にすれば、まずはCodexの「食品衛生の一般原則」である。業界別手引書の前に、まずはCodexである。
(日本の食品衛生法は、Codexの考え方を踏まえた上で改正されている。これは法改正に関わった方々に、深く感謝しなければならないと思う)
CodexのHACCP指針は、世界に一つだけである。世界のどこを見ても、それを事業者の規模で2つに分けた国はないと思う。あるのは「事業の業態によって、アプローチを変える(柔軟なアプローチを容認する)」「事業者の規模に応じて、時間の猶予を調整する(零細事業者には猶予期間を長くとる)」という考え方だけである。
「〇〇をやっていれば、HACCPをやっているとみなす」という“柔らかい”考え方
著者が20年ほど前に、ドイツの人に「調理温度の記録、廃棄物管理(ゴミ捨て)の記録がちゃんとしていれば(HACCPをやっているとみなさせることが多い)」と聞いたことがある。もちろん今は状況は変わっているだろうが、「それくらいやっていればOK」というよりは、「これはやっていないといけない」という話だろう。
イギリスでは、公的な組織から「より安全な食品、より良いビジネス(Safer food, better business、SFBB)」という文書が出されていて、飲食店は、この記録用紙を利用していれば、「HACCPをやっているとみなされやすい」というものだ。
一時期、「日本版SFBB」を開発するような動きもあったと記憶しているが、立ち消えになったのでしょうか?
とはいえ、日本は実質すべての事業者にHACCP制度化を規定している。HACCP制度化に対応していなければ、コンプライアンス違反とみなさなければならないはずだ。
では、何を持って「HACCP制度化に対応している」とみなすのか?
「HACCPの考え方を取り入れた衛生管理」という曖昧な、理解が困難な枠組みは、いったんスタート地点に戻ってもよいかもしれない。
著者は「何が何でもHACCPをやれ」とは考えていない。「CCP管理をしていなくても、消費者の安全を説明できるなら、HACCPをやっているのと同等と容認すればいい」という考えしか持っていない。
なぜなら、HACCPには「科学」しかない。微生物を制御する、化学物質を制御する――微生物も化学物資も、想定外の挙動はしない(未知の生物や物質が出てきた場合は別の話だが)。
既知の知識で、既知の物質を制御する――それがHACCPであり、食品事業者は最善を尽くせば、それで十分のはずである。「想定外を想定せよ」と主張する人もいると思うが、私はそれは極めて困難なことだと思っている。
ただ、「まさか停電中に黄色ブドウ球菌の毒素が発生するとは……」「まさか乾燥物にノロウイルスがいるとは……」「まさか湯引きした肉の寿司でカンピロバクターが出るとは……」「まさか生の挽き肉のハンバーグにO157がいるとは……」「まさか湧き水に病原菌がいるとは……」…………通用するはずがない。
食中毒事例の中には、従業員がルールを守らなかったために起きたものもある。最近は「食品安全文化」の話題もあるが、ルールが守られない事例の多くは、ルールが悪い(守れない・守りにくいルールを設けている⇒管理者側の責任)か、従事者が組織に不満があり意図的にルールを破ったか、が原因のように思う。手洗い不備でノロウイルスが起きることがあるが、そもそも手洗いの施設・設備の不備が原因の場合もある。
既知の知識や経験をフル動員すれば、「いま見えていないリスク」が見えるようになるかもしれない。それが「HACCPの考え方」を取り入れるための、最初の一歩かもしれない。
まあ、食品安全文化の議論は別の機会に譲るとして……
いずれにしても、著者は「食中毒、食品事故を防げるなら、何でもよい」と考えている。言い換えると「事故を起こさないという説明ができれば大丈夫」という意味である。
(食品の安全性を説明しようとすれば、自ずとHACCPのような考え方になることも間違いない)
「HACCPの運用」は、安全な食品を作るための手段に過ぎない。「HACCPをやること」が目的ではない。モノを切るだけならハサミでもカッターでも、何だったら手で破っても、嚙み千切っても構わない。外を歩くときは、高価な靴でもペラペラのサンダルでも、何だったら裸足でも構わない。移動するなら車でも飛行機でも、何なら歩いたっていいし、超能力者なら瞬間移動したって構わない。
食品安全は作法やマナーではない。消費者の健康や生命を守るために、あるはいは何か有事の際に自分たちの組織を守るために、どのような仕組みが必要か、どのような説明ができればよいのかを考えていけば、自ずとHACCPの考え方を取り入れることになると思う。
まずは、最小限、必要なモノから揃えていけばよいのではないだろうか。
幸い、HACCPにゴールはない。組織が続く限り、永遠にハザード分析の見直しを続けなければならない。見直して、改善していけば、徐々に「より良い食品安全の体制」に進化していくはずだ。
一つ、書き忘れました。業界別手引書の問題点の一つは、「見直し(振り返り)」の要素が弱い点だと思います。見直しの要素はたしかに盛り込まれていますが、現状の手引書は「見直しは、ちょっと触れているだけ」なので、読んだ人が「構築に目が向きがちになるのでは……」という印象です。


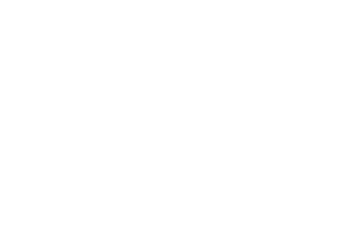 お問い合わせはこちら
お問い合わせはこちら