公定法の検査結果であれば、信頼されるの?
更新日時:2025.10.13
微生物検査は、バラツキが生じる要因がたくさんある
公定法や標準法、参照法と呼ばれる微生物検査の方法は、その多くが準備や手順が煩雑で、培養などに時間がかかる場合があります。その手順も、相当の手技やコツが必要な場合もあります。
微生物検査では、培地や試薬の調製、培地への菌の接種、コロニーカウントなど、さまざまな手順が存在します。そして、そのすべての手技が、検査結果のバラツキに影響を及ぼすのです。例えば、ピペット操作であれば、きちんとメンテナンスされたピペットで、きちんと訓練を受けた人がピペット操作をしなければ、結果にバラツキが生じる可能性があります。
培地や試薬を調製する時も、専門知識なしに作業すると、「正しい結果が出ない培地や試薬」を作ってしまう場合があります。そして、専門知識が不足していたら、「正しくない試薬や培地」「正しくない手順」であることに気づかないまま、作業を進めて、結果を出してしまうこともあるのです。
あからさまに「間違った結果」ではないにしても、検査担当者の手技が安定していなければ、検査結果にバラツキが生じます。検査では手順が多いので、一つひとつの手順で少しずつばらつきがあれば、最終的に大きなバラツキとなってしまいます。
「公定法でやらないといけない」と思い込んでいる関係者は多いです。一方で、「決められた手順どおりにやれば、必ず正しい結果が出る」とは限りません。
つまり、公定法を実施していたとしても、取引先から「検査結果が信頼できる」と認識してもらうためには、「公定法で定める培地や手順に従うだけでは不十分」ということです。
そして、「自分の作業が正しいか? 安定しているか?」を客観的に評価・説明するのは、実は非常に難しいことなのです。
正しい技術を継承できているか?
適切な教育・訓練を受けていない担当者が検査をした場合、誤った結果を出してしまう、結果にバラツキが生じてしまう可能性があります。
また、微生物検査は、属人的な技術が多いです。そして、昨今、その技術継承が大きな課題となっています。あるいは、「先輩たちの個人的なコツやノウハウが、代々受け継がれてきたが、なぜその作業が必要かは、誰も知らない」なんてこともあるようです。
専門的な知識や技術の継承は、多くの検査室に共通の課題となっているのが現状です。
検査室の信頼性は「手技の確かさ」と「組織としての検査室の質の維持」の両面が必要
つまり、検査結果が信頼されるためには、 「正しい結果を得るための装置や器具、手技を確保している」という観点と、「常に正しい結果を得られる組織体制、組織としての継続性を確保している」という観点の両方の両方が必要なのです。後者は「マネジメントの仕組み作りが必要」と言い換えることもできます。
しかし、ただ単に「うちのスタッフが頑張って検査しています」では、信頼されるわけがありません。「〇〇協会で手技を学びました」「××検査会社の検査講習に参加しました」というのは、国内では信頼されるかもしれません。しかし、その協会や検査会社を知らない人が聞いたら、それこそ日本の事情に詳しくない海外の関係者には、それでは信頼してもらえないかもしれません。
そこで、信頼できる検査室であることを社外に示す「信頼のモノサシ」の一つとして、ISO 17025のような試験所の運営に関する国際認証の必要性が、今後はますます高まると考えられています。最近は、FSSC 22000などの国際規格では、「検査結果はISO 17025に相当する規格を有する機関で得ること」などを求める場合もあるようです。
ISO 17025に関しては、下記を参照してください。
https://www.jab.or.jp/service/laboratory
信頼できる簡易検査キットの有用性
しかし、「自主検査の信頼を保ちたい」といったニーズであれば、必ずしも試験所認定まで考える必要はない場合が、ほとんどでしょう。
そうした場合は、迅速・簡便な出来上がり培地を使ったり、様々な自動化装置などで、十分に目的を果たせるのではないでしょうか。
培地調製が不要な簡易的な培養検査キットとしては、例えばネオジェンジャパン(旧・スリーエムジャパン)のペトリフィルム、島津ダイアグノスティクス(旧・日水製薬)のコンパクトドライ、JNCのMC-Media Pad(旧・サニ太くん)、キッコーマンバイオケミファのEasy Plate(旧・Medi・Ca)、関東化学のCHROMagar、エルメックスのPro・media、極東製薬工業のバイタルメディアをはじめ、培地メーカー各社が、それぞれ個性的なシリーズを展開しています。
自動化装置ということであれば、ビオメリュー・ジャパンは最確数(MPN)法を自動化した「TEMPO」や蛍光免疫測定法を自動化した「VIDAS KUBE」、酸素電極法を自動化したバイオ・シータの「DOX」、大腸菌群の公定法を自動化した協和医療器の「バイオプティ」をはじめ、検査対象も原理も装置も多種多様です。
上記のキットや装置は、あくまでも一例です。これまでも、これからも、検査キットは進化していきます。逆に、ユーザーとしては、「どのようなキットを使えばよいか?」に悩むかもしれません。
価格以外の評価基準、判断基準を持っておく必要があるでしょう。


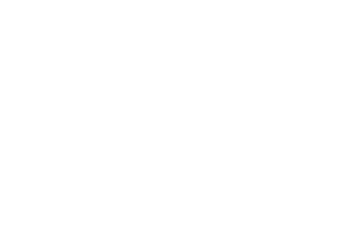 お問い合わせはこちら
お問い合わせはこちら