食品安全文化、何をやればよい?
更新日時:2025.10.17
2020年に改訂されたコーデックスの「食品衛生の一般原則」(General Principles of food hygiene, CXC 1-1969)では、新たに「食品安全文化」(food safety culture)という概念が採用されました。
それ自体は新しい概念というわけではなく、国際的な食品安全の分野では、すでにGFSI(世界食品安全イニシアチブ)などでも以前から提唱・定着している考え方です。
コーデックスの「食品衛生の一般原則」では、以下のような記述があります。経営者層が理解しなければならない考え方であることは明らかです。
[仮訳]
食品安全に対する経営層のコミットメント
食品衛生システムがうまく機能するための基本は、安全で適切な食品の提供における人間の行動の重要性を認める前向きな食品安全文化の確立と維持管理です。以下の要素は、前向きな食品安全文化を育む上で重要です。
・安全な食品の製造と取り扱いに対する経営層とすべての要員のコミットメント
・正しい方向性を設定し、すべての要員を食品安全規範に関与させるリーダーシップ
・フードビジネスに関連するすべての要員による食品衛生に関する重要性の認識
・逸脱や期待の伝達を含む、フードビジネスにおけるすべての要員間のオープンで明確なコミュニケーション。および、
・食品衛生システムの効果的な機能を保証するための十分なリソースが利用可能であること
では、食品安全文化に関しては、どのような活動をすればよいでしょうか。
FSSC 22000の審査関係者のお話では「食品安全文化の概念をするからといって、必ずしも特別な変更が必要になるわけではない」ということでした。
FSSC 22000の追加要求事項でも食品安全文化は盛り込まれていますが、事業者に新しい取り組みを要求するものではありません。審査でも「食品安全文化についてはいかがですか?」「食品安全文化として、どのようなことをされていますか?」といったナンセンスな質問を受けることはありません。
審査では「食品安全文化が浸透しているか?」が判断されるだけです。食品安全文化に対する不適合が判断されるのではなく、コミュニケーションやトレーニング、従業員フィードバック、活動のパフォーマンス測定など、関連する項番に沿った指摘が行われるだけです。
HACCPに取り組む会社では、どこも「食品安全方針」を掲げているでしょう。要は、この方針を、いかに浸透・定着させているか、教育・訓練しているかを明確にすればよいのでしょう。


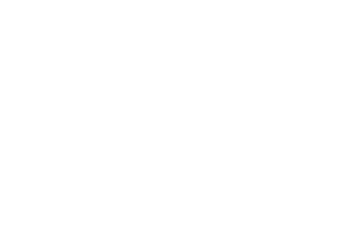 お問い合わせはこちら
お問い合わせはこちら