営業停止中に営業して逮捕?~「コンプライアンスの意識」「法律の背景の理解」という議論が必要では~(2025年6月)
更新日時:2025.7.30
ノロウイルスによる食中毒を起こして営業停止命令を受けていた事業者が、営業停止期間中に弁当を売っていたとして、大阪府警は6月16日、食品衛生法違反容疑で経営者ら3人を逮捕する、という報道がありました。この事業者はミシュランガイドに掲載された有名な老舗ということもあって、衛生管理の在り方や、その後の対応の在り方などが話題となりました。
・読売新聞オンライン
https://www.yomiuri.co.jp/national/20250616-OYT1T50036
この事件を衛生管理の問題、食品安全文化に絡めて言及することはできますが、「そもそも法律を守っていない」「そもそも法律の背景を理解していない」という事業者である以上、「HACCP以前の問題」「食品安全・食品衛生で語るのは論外」と言われても仕方がないと思います。
法律を守らない、コンプライアンスの概念が希薄な経営者が、組織全体で取り組むHACCPや衛生管理にコミットしているとは思えません(現場のスタッフの中には一生懸命に取り組んでいた人も多かったと思いますが)。
しかし、これはレアケースでも、「対岸の火事」でもないと思います。既に日本ではHACCP制度化が施行されています。「HACCPを知らない、HACCPを運用していない食品事業者」=「法律違反、コンプライアンスの意識が希薄」と指摘されても仕方ないのではないでしょうか?
HACCPの指導に携わる方々は、それくらいの厳しさでHACCP制度化を向き合ってもよいのではないでしょうか?
現状の食品衛生法では、HACCPをやっていないからと言って、即座に罰則が付されることはないでしょう。「罰則がないから(HACCPを)やらない」と考えている事業者はいないと思います。しかし、「罰則のない法律」である以上、守らない事業者が出てきても不思議ではありません。
だからと言って、筆者は「HACCPを実施していない事業者には罰則を設けよう」とは考えていません。HACCPは「自分のため」「顧客のため」にやるものです。行政の方を向いてやるものではありません。HACCPは「法律で義務化されていなくても、食品安全を理論的・体系的に確保しようと思ったら、自ずと取り組んでいるもの」だと思います。
そして、HACCP制度化が「罰則のない法律」であることには、行政の意図があるはずです。それはHACCP制度化や食品安全の取り組みが、「行政が主導するもの」ではなく、「事業者が自主管理で取り組むもの」というメッセージと捉えることもできるのではないでしょうか?
●HACCP制度化で「行政が主導の時代」から「事業者の自主管理の時代」へ
2018年の食品衛生法改正で、実質的に全ての食品営業に対してHACCPに沿った衛生管理――具体的には衛生管理計画の作成や実施が義務付けられました。これを「行政は、食品安全の取り組みを一層厳しくした」と捉えると、HACCP制度化の本質を見誤ると思います。
このたびのHACCP制度化は、「行政が主導する時代」から「HACCPを事業者の自主管理に委ねる時代」へのパラダイムシフトです。
食品施設の監視指導で問題なかったからと言って、それは衛生管理について「行政による『お墨付き』をもらった」ということではありません。製品の品質や安全に最終的な責任を持つのは、事業者自身です。
●総合衛生管理製造過程(いわゆる「マル総」)も目的は「規制緩和」だった
1995年(平成7年)に食品衛生法で新たに「総合衛生管理製造過程」の承認制度(いわゆる「マル総」)」が創設されました(2018年の食品衛生法の改正に伴い、2020年(令和2年)に廃止されました)。
この制度は、当時のトレンドであった「規制緩和」も考慮していました。規格基準が規定されていた食品、すなわち乳・乳製品、清涼飲料水、食肉製品、魚肉練り製品、容器包装詰加圧加熱食品(缶詰・レトルト食品)については、HACCPの考え方を適用して科学的根拠を備えていれば、必ずしも規格基準に従わなくとも食品を製造できる、という承認制度でした。
しかし、実際には、この制度が「規格基準に従わないが、安全性を担保した食品」の製造に生かされることは、ほとんどありませんでした。承認件数のピーク時には1000件を超えていましたが、そのほとんど全ては「規格基準に沿って製造している」という状況でした。残念ながら、マル総が「規制緩和」の役目を果たしたとは言えないでしょう。
それどころか、マル総の承認施設であることや、業界団体が作成した「承認マーク」をPR材料に使うことで(それ自体は悪いことではありませんが)、2000年代の初頭は「HACCPの承認取得が目的化する」という指摘もされていました。
この頃、「HACCPは(認証や承認を)取るものではなく、(運用を)やるもの」といった表現も、頻繁に耳にしたと記憶しています。
●「法律の背景の理解」をもっと議論すべき?
そもそも法律とは「法律に書いてなければ、何をしても許される」というものではありません。
法律には「信義誠実の原則」という考え方があります。私は法律の専門家ではないので、受け売りになりますが「相互に相手方の信頼を裏切らないよう誠実に行動すべき」という考え方だそうです。
食品衛生法では、必ずしも「食中毒などのリスクがある食品」の全てを、製造や喫食を禁止しているわけではありません。生食用の牛肉の規格基準が設けられていたり、牛・豚の生レバーの販売禁止、といった法律はあります。しかし、これらは2011年のユッケによる腸管出血性大腸菌の食中毒を契機に規定されたものであり、それ以前はわざわざ法律では禁止していませんでした。それは、「それ以前は安全だった」ということではありません。社会全体の共通認識として「危ないから食べない」という行為が一般的であったからと考えられます。そう考えると、もしかしたら「生食用牛肉の規格基準」や「牛・豚の生レバーの販売禁止」は、本来は設ける必要のない法律だったのかもしれません。
しかし現実には、牛・豚の生レバーの販売が禁止された当時、「もうすぐ牛レバーが食べられなくなるから食べに行こう」「牛レバーが禁止になったから、代わりに豚レバーを食べよう」といった、食中毒リスクを軽視したような「駆け込み需要」があったことも事実です。
「法律の背景」を理解せずに「法律だから守る」「法律に書かれていないことは、何をやっても構わない」という考え方は、決して許容されるものではありません。


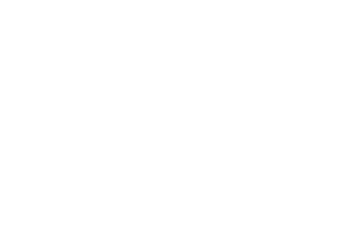 お問い合わせはこちら
お問い合わせはこちら